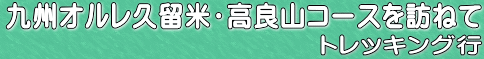 (2022・6) (2022・6) |
|
| 毎週のように歩きに出ているワタシですが・・・。 今回、初めて九州オルレのコースに手を出しました。 オルレというのは、韓国・チェジュ島発祥のトレッキング。もともとは「通りから家に通じる狭い路地」という意味だったのが、島でのトレッキングコースの総称として呼ばれるように。そのオルレが九州に上陸し、九州内でも様々なコースが設定されています。 4月に武雄温泉駅スタート・ゴールのJR九州ウォーキングに参加した際、九州オルレ武雄コースのルートの一部をコースに使っていまして、それをきっかけに、九州オルレのことをいろいろ調べてみました。なるほど、これならワタシでも歩けそうだなぁということで、参加の機会を窺っていました。 今回は、まず手近なところで、久留米・高良山のコースにチャレンジすることにしました。 この日は小学校も土曜授業の日で、ワタシの単独行に。果たしてどうなったのやら・・・。 なお、トレッキング部分についてはこちらも参照ください。 |
|
 |
6月18日、まずは朝、地元・箱崎から。 7時25分発、普通1151M列車博多行き、813系6両での運転、前3両はRM2219編成でした。 やっぱり、椅子少ない車両に当たっちゃいますね・・・まぁ博多で乗り換えるからいいか。(^^; |
 |
1151Mは博多駅6番ホームに到着。 すぐさま、向かい側の5番ホームに停車していた7時33分発、快速1381M列車荒木行きに乗り換えます。博多始発のこの列車、811系PM7編成4連での運転でした。 |
 |
博多を出て、右手には南福岡車両区竹下車両派出の留置線が見えてきます。 洗浄線に停まって出番を待つ「ななつ星 in 九州」のすぐそばに、DD200-701が停まっています。同機は前週末に続いてこの週末も、「ななつ星」の博多への入出区のエスコートを担当していました。 |
 |
途中の二日市で、先行していた普通2325M列車熊本行きとの接続。 2325Mのほうは、415系Fo-123編成4連での運転でした。 2325Mは箱崎7時3分発ですが、ワタシが乗車した1381Mが7時47分にはここ二日市で追い抜くことに・・・今回は乗り継ぎその他の都合で1381Mに乗りましたが、それを考えなくていいなら、415系でのんびり行くのもありでしたね。 2325Mにそのまま乗っていくと、熊本到着は9時59分・・・うん、全然ありでしょう。箱崎から3時間も乗ってりゃ着いちゃうんですもん。 |
 |
8時8分、1381Mは久留米駅3番ホームに到着しました。 ここで降りたほとんどのお客さんは、改札口に向かって階段を登っていきますが、ワタシは乗り継ぎなんで・・・。 |
 |
こちらへやってきました。 下り方にある、欠き取り式の2番ホームです。久大本線の列車が久留米折り返しの際に使用するホームですね。先日、このウォーキングの際にも、筑後吉井からの帰りの列車でここに到着しました。 |
 |
2番ホームで列車を待っている間に、3番ホーム側をこちらが通過。 北九州貨物ターミナル発で鹿児島へ向かう、高速貨4093列車ですね。この日の牽引はEF81-453。 門司機関区のEF81ですが、EF510形300番台の増備が迫っているなか、JR化後に新製されたグループである500番台でも運用落ちするカマが出ていますので、安穏とした状況ではありませんね。 |
 |
ここ久留米からは、8時33分発、普通1833D列車うきは行きに乗車します。 前運用である、うきはからの普通1830D列車が、キハ200-1554+554の2両で入線してきました。 この2両も、もとはキハ200で最初に新製された0・1000番台で、転換クロスシートを装備していましたが、ロングシート化改造されて車号が+550となった車両です。 運転室背後には、鉄道友の会ローレル賞受賞のプレートがつけられていました。 |
 |
|
 |
1833Dは定刻に久留米を発車。 しばらく鹿児島本線と並走したあと、左へ分かれて行きます。 その先少し行くと、西鉄天神大牟田線がオーバークロスしていきます。 |
 |
久留米高校前に停車し、こちらは南久留米。 善道寺始発でやってきた、普通1834D列車久留米行きと行き違い。向こうはキハ220-201+205での運転でした。 確か向こうの列車は、久留米到着後に鳥栖へ回送され、午後から2両別々にまた久大線の運用に入るんだったと思います。そう、昼間に鳥栖駅の留置線に停まっている、アレですね。 |
 |
8時43分、1833Dは久留米大学前に到着しました。 1面1線のホーム、列車は乗降が終わるとすぐに発車していきます。 この駅は2000年3月に開業していまして、現在は特急「ゆふ」が上下1本ずつ停車するという駅でもあります。久留米大学御井キャンパスをはじめ、周辺はさまざまな学校施設がある文教地区になっています。 今回の九州オルレ久留米・高良山コースは、この久留米大学前駅がスタート。駅舎内にはオルレ参加者向けのスタンプも設置されています。 |
 |
駅をあとに、高良山の方向へ歩き始めます。 こちら、南筑高校。久留米市立の高校です。あの藤井フミヤ氏の母校としても知られるところですね。 そっかぁ、ここにあったのね、南筑高校って・・・。 |
 |
さらに進んで、こちらは県道86号と交差する御井小学校西交差点。 写真左側にある看板には、「筑後国一の宮 高良大社」の文字が見えています。 そう、今回のコース途中にある高良大社は、1600年以上の歴史があり、朝廷からの尊崇厚く、この地域の一の宮として崇められてきた経過があります。 交差点から山手へ向かうと、こちらの石造大鳥居があります。 江戸時代の1655(承応4)年に、当時の久留米藩主・有馬忠頼が寄進したとのことで、国指定文化財となっています。 |
 |
|
 |
九州自動車道をくぐり、さらに山手へ。 放生池にかかる、御手洗橋を渡ります。 池のなかには、アジサイが植えられていまして、ちょうど花をつけている光景が見られました。 |
 |
ここからはいよいよ、本格的に山の方へ入って行きます。 オルレのコースの途中には、番号の書かれたレスキューポイントの看板が各所に立っています。ケガなどの緊急通報時には、近くのポイントの番号を伝えて場所を知らせることができるようになっています。 で、赤と青の矢印がついていますが、これがコースの向きを表します。青が正方向、赤が逆方向で、ゴールから逆向きにコースを進むことも可能になっています。 高樹神社の鳥居をくぐり、いよいよ山道へ。 しばらくは、石段を登る形となります。 |
 |
|
 |
石段の途中にはいくつか見どころがあるんですが、こちら。 高良山あじさい園です。 やはりちょうどシーズンということで、多くの花が咲いていました。 |
 |
コースをさらに進むと、こちら。 孟宗金明竹林があります。 ここの竹は、表皮の外層が突然変異して黄色となり、それが節間毎に緑と交互になっているという珍しいもので、国の天然記念物に指定されています。 |
 |
このあと、高良大社本宮の横から、高良山の上の方をめざすルートになるんですが、ここでどうやら、ワタシは道を間違えたようで、本来のルートとは逆回りでめぐることになりました。スマホで、ルートマップとGPSの地図アプリとを照合してルートを確認していたんですが、GPSの精度が落ちていたようで、ちょっと違うところへ入ってしまいました。(^^; その逆回りルートの途中には、こうしてロープがかけられているところも。 なかなかにハードな道のりでした。 |
 |
そうして辿り着いたのが、こちら、杉城跡です。 久留米の街並みを展望することができるんですが、写真中央には、久留米成田山の慈母大観音像があるのが分かります。高さが62mあるということで、遠くからでもよく見えます。 |
 |
さらに進んで、山頂に近い久留米森林つつじ公園へ。 ここには、かの夏目漱石が詠んだ俳句の句碑があります。 菜の花の 遥かに黄なり 筑後川 漱石は熊本に赴任していた際、教師の同僚でもあり、兄と慕った菅虎雄の故郷であるこの久留米に5回ほど訪ねたのだそうで、この句も1897(明治30)年にこの高良山を訪れた際、春の筑後川の景色を眺めて詠んだもののようです。 |
 |
そこから少し歩くと、高良山の山頂。 標高312m、ここが頂上です。 山頂から、少し遠方を見下ろしてみます。 山頂を吹き抜ける風が、とても心地よくてですねぇ・・・。ここまで登ってくるのに、暑かったこともあってかなり汗をかいていたんですが、この山頂の風を浴びて、そうしたきつさやつらさはどこかへ飛んでいってしまいました。 これは、山を登ってみないと分からない感覚ですよねぇ。(^^; そこから、本当ならば山頂のさらに先、しょうぶ池までまわってくるルートになっていたんですが、そちらへいくのを完全に忘れていまして・・・まぁ今回は、このくらいにしとこうかと。 |
 |
|
 |
山頂から、高良大社の奥宮をめぐり、逆回りコースのまま、高良大社本宮まで降りてきました。 この本宮の前にも展望台がありまして、久留米の街並みを一望することができます。 |
 |
本宮から少し降りたところに、こちらがありました。 「高良山茶屋 望郷亭」。1948(昭和23)年創業、高良大社の目の前で営業を続けてきたお店です。 うどんやだご汁といった食事メニューも扱っているんですが、お店のメニューで「高良山茶屋名物」と謳われているのが、ところてん(300円・税込)。対馬産のテングサを使用した自家製のものだとのこと。 だったら、せっかくなんでいただいてみるかと。 登場したのが写真の品。 とにかく、真夏日(この日の久留米の最高気温は33.9℃!)になってしまったくらい暑かったもんで、この冷えたところてんは本当にありがたかったです。 プルプルな食感のところてんに、ポン酢と生姜。この生姜は、冬場だけでなく夏でも、発汗作用を促す効果があるのだそうで、山を登ったあとの体にも良いんですよね。本当に沁みました。(^^; |
 |
|
 |
ところてんを食べ終わって、さらに山を下っていきます。 文字通りの山道なんですが・・・途中にはこんな橋もありましてね。 山道を抜けると住宅街。 そこをさらに歩いて・・・。 |
 |
久留米大学前駅をスタートして約3時間で、11時47分にゴールの御井駅に辿り着きました。 標柱に、オルレの青と赤のリボンがかかっていますね。 で、ここから列車に乗って久留米方面へ向かおうと思ったんですが、列車は12時43分までない・・・。 |
 |
炎天下ということでさすがに待ちが長すぎるんで、並行して走っている西鉄バスのほうに乗ることにしました。 御井駅前バス停から12時5分発、行先番号24番の大学病院行きに乗車します。西鉄バス久留米吉井営業所の9100号車がやってきました。 |
 |
そのまま、バスで西鉄久留米バスセンターまでやってきました。 時間的にはそろそろお昼を食べたいんで、スマホでいろいろ検索しながら探していたんですが、なかなかこれという決め手がなく、そのままJR久留米駅方面へ歩いて移動・・・。 |
 |
|
 |
気が付けば、JR久留米駅が近いところまで来ていました。 たまたま信号待ちで見つけたこちら。「明治通り」という通りの標記をしている板、よく見ると絣の柄になっていました。 さすがは、久留米絣で有名なところだなぁと。 |
 |
そして、辿り着いたのがこちら。 「中央亭」です。 ここは、日田焼そばと餃子を出しているお店。先にも名前が出た藤井フミヤ氏が、久留米に帰省するとやってくるといわれるお店ですね。 ワタシは以前、このときにもここで焼そばをいただいてたんですが、今回再訪ということにしました。 |
 |
もうお腹ペコペコなんで、注文したのは焼そばの大盛、950円(税込)。 もやしシャキシャキ、麺はしっかりカリカリに焼かれています。ソースだけでなく、胡椒も効いていて、とてもいい感じ。 麺の焼け具合、そしてこの胡椒の効き具合・・・日田焼そばのお店だと、今まで食べたなかでは、ワタシ自身ここのお店が一番好みかもしれないなぁと思いました。 |
 |
焼そばを食べ終わって、そのまま歩いて久留米駅までやってきました。 とにかく暑い・・・早いこと、引き上げるとしましょう。 |
 |
ホームへ降りてくると、そこへ久大線からの「ゆふいんの森2号」博多行きが入線してきました。車両はおなじみのキハ72系5両。 昼の日が高い時間の上り、ということもあるのかもしれませんが、かなり空席が目立っていましたね・・・。 |
 |
「ゆふいんの森2号」が発車したあと、ワタシが乗る列車が到着。 13時52分発、区間快速(久留米→博多間快速)1334M列車海老津行き、813系6両での運転、前3両はRM2224編成でした。 椅子の少ない車両でしたが、一つ前の荒木始発ということもあってどうにか席をゲットできました。 |
 |
途中、鳥栖ではこちら。 今やここではすっかりおなじみ、「SL人吉」編成が留置線で折り返しを待つ光景です。 この状況も果たしていつまで続くのか・・・。 |
 |
博多で1334Mを降り、靴を買いにいきました。 ウォーキングシューズが、もう履きつぶしたような状態でボロボロになってましたんでね、新しいのを調達してきました。 博多からは、15時9分発、普通1228M列車福間行きに乗車。 813系RM113+3503編成計6両での運転でした。 |
| ということで、初めての九州オルレ参戦の様子でした。 今回のコースも、実際歩いてみるといろいろ見どころもあり、トレッキングでしっかり汗を流して、という目的もしっかり達せて、とてもいい感じでした。 今回のコースは駅がスタート・ゴールというとっつきやすい内容でしたが、九州オルレのコースはそういうところばかりじゃありません。今後、よく研究して参戦の段取りをつけたいと思います。 でも、そろそろ暑い季節になって、歩くにはなかなか厳しくなってきたかな・・・。 寒いとまだやりようがあるんですけどね。 |
|
| <おわり> |
|